半夏生(はんげしょう)という言葉、聞いたことはありますか?
日常生活ではあまりなじみがない言葉かもしれませんが、実は古くから日本の暮らしや自然のリズムに深く関わってきた大切な節目の日なんです。
この日には、地域によってタコやうどん、サバといった食材をいただく風習があり、それぞれに意味や願いが込められています。
また、気候や農業、そして古くから伝わる迷信などとも結びついており、知れば知るほど興味深い文化です。
この記事では、「半夏生って何?」という疑問にやさしく答えながら、行事食の理由や地域の風習、昔ながらの言い伝え、
そして現代の私たちにできる楽しみ方まで、丁寧にご紹介します。初めての方でも安心して読める内容なので、ぜひ最後までお付き合いくださいね。
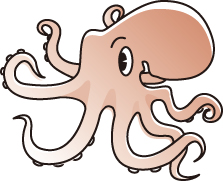
半夏生(はんげしょう)とはどんな日?
半夏生(はんげしょう)は、夏至から数えて11日目にあたる日で、2025年は**7月1日(火)**です。
日本の伝統的な暦「雑節(ざっせつ)」のひとつで、農業の節目として古くから重要な意味を持ってきました。
農村では「半夏生までに田植えを終えるのが良い」とされ、季節の進み具合や農作業の計画を立てるうえで欠かせない目安でした。
この日は、農作業を一段落させ、体を休める時期としても位置づけられていました。
また、梅雨の終わり頃にあたることが多く、湿度や気温が一気に高まる時期でもあります。
体調を崩しやすくなることから、栄養価の高い食事をとって体力を補う、そんな“暮らしの知恵”が各地の風習として残っているのです。
半夏生の語源と植物「半夏生」との関係
「半夏生」という言葉には、暦の区分だけでなく、植物に由来する意味もあります。
ひとつは薬草「半夏(はんげ)」として知られるカラスビシャクという植物。古くから漢方薬としても使われてきた野草です。
もうひとつは「半夏生(ハンゲショウ)」というドクダミ科の多年草で、6月末から7月にかけて開花します。
この植物の特徴は、葉の一部が白く変化すること。まるでお化粧をしているように見えることから「半化粧(はんげしょう)」とも呼ばれます。
開花時期が半夏生と重なることから、季節を表す草花として親しまれてきました。
現代でも、湿地帯や日本庭園などで鑑賞用に植えられており、梅雨の風情を感じさせてくれる植物のひとつです。
地域別・半夏生の行事食と意味
半夏生には、地域ごとに特徴的な「行事食」があり、食べるものが異なるのも面白いところです。
それぞれの食べ物には、五穀豊穣や健康への願いが込められており、古くからの風習として根づいています。
近畿地方|タコを食べる理由
関西地方では、半夏生の日に「タコ」を食べる習慣があります。
-
タコの足が八本あり、地に根を張る稲のようにしっかり育つように
-
吸盤にあやかって「たくさん実る」ように
-
タウリンが疲労回復や肝機能に良い栄養食としても効果的
農作業の節目にふさわしい、体をいたわる食材なんですね。
香川県|うどんを食べる理由

香川県では、半夏生の日に「うどん」を食べる風習があります。
うどん県として有名な香川ですが、この風習には農作業への感謝の気持ちが込められています。
麦の収穫を終えた農家が、新麦でうどんを打ち、手伝ってくれた人たちにふるまったことが由来です。
現在では7月2日が「うどんの日」として記念日登録され、地域イベントも開催されています。
暑い時期でも食べやすく、冷やしうどんやぶっかけうどんなどアレンジの幅も広いのが魅力ですね。
福井県|サバを食べる理由
福井県の大野市などでは、半夏生に「焼きサバ」を食べる風習があります。
ビタミンB群やEPA・DHAが豊富に含まれるサバは、代謝アップ・夏バテ防止にもぴったり。
この時期、農繁期を終えた体を癒すために、栄養たっぷりの青魚でパワーをつけるという知恵が息づいています。
福井では「半夏生サバ」としてブランド化されているほどで、地域全体で大切にされている文化です。
行事食に込められた栄養の知恵
タコ・うどん・サバは、それぞれ暑い時期にぴったりの栄養食でもあります。
-
タコ:高たんぱく・低脂質。タウリンが肝機能や疲労回復に◎
-
うどん:消化がよく、エネルギー補給にも最適。冷やしてもおいしい
-
サバ:EPA・DHA・ビタミンB群が豊富で、代謝や血流をサポート
昔の人の知恵って、本当に理にかなっていますよね。
半夏生にまつわる迷信・言い伝え
昔の人は、半夏生の日を「物忌みの日」として、注意すべき日と考えていたそうです。
-
「空から毒気が降る」と言い、井戸にフタをして水を守った
-
種まきや野菜の収穫は避けた
-
「毒草が生える」として山菜採りも控えた
迷信のように思えますが、梅雨明け前の高温多湿で食材が腐りやすくなるこの時期。
実は「安全を守る生活の知恵」でもあったのかもしれません。
半夏生の過ごし方|現代の楽しみ方アイデア
今の暮らしでは農作業をする人は少ないですが、季節の行事としての半夏生を楽しむことはできます。

-
タコやうどん、サバを使ったごはんで季節を味わう
-
子どもに行事の意味を話してあげる
-
SNSで「#半夏生ごはん」を投稿して共有
-
暑さに負けないよう、栄養バランスの良い食事を意識する
ふだん何気なく過ぎてしまう1日も、「今日は半夏生」と思うだけで少し特別な日に変わるかもしれません。
日本各地の半夏生行事・風習まとめ
各地で受け継がれているユニークな風習をご紹介します。
-
奈良県御杖村:「半夏生踊り」という伝統芸能が今も行われている
-
奈良県:「半夏生餅(さなぶり餅)」という小麦餅を作る風習もあり
-
北陸地方(富山・石川):焼きサバ文化が根づいている
-
香川以外の地域でも「うどん+天ぷら」のセットで祝うことがある
どの地域も、その土地ならではの工夫や願いが感じられます。
【コラム】旧暦と新暦で半夏生はどう違う?
昔は、旧暦(太陰太陽暦)で半夏生を計算していたため、現在のカレンダーとは日付がズレていました。
現在では、「太陽黄経が100度に達する日」として天文学的に定義されており、毎年少しずつ日付が変わります。
-
2025年の半夏生:7月1日(火)
-
2026年の半夏生:7月2日(木)
気になる方は、毎年カレンダーや暦をチェックしてみてくださいね。
よくある質問(FAQ)
Q1. 半夏生には何を食べるのが正式ですか?
→ 地域によって異なりますが、タコ・うどん・サバが代表的です。
Q2. 家で簡単にできるおすすめ料理は?
→ タコの酢の物、冷やしうどん、焼きサバ定食などが人気です。
Q3. 昔の迷信は今でも信じられているの?
→ 現代では迷信とされますが、注意喚起や安全を守る知恵として語り継がれている地域もあります。
まとめ|日本の季節感を大切にする心
半夏生は、農作業の節目であり、季節の変わり目を意識する大切な日でもあります。
タコ・うどん・サバといった食文化に触れることで、昔の人の暮らしの知恵や自然への感謝を思い出させてくれます。
今年の半夏生、あなたも少しだけ“季節のリズム”を意識して過ごしてみませんか?
きっと、日々の暮らしに新しい発見や楽しみが生まれるはずです。


