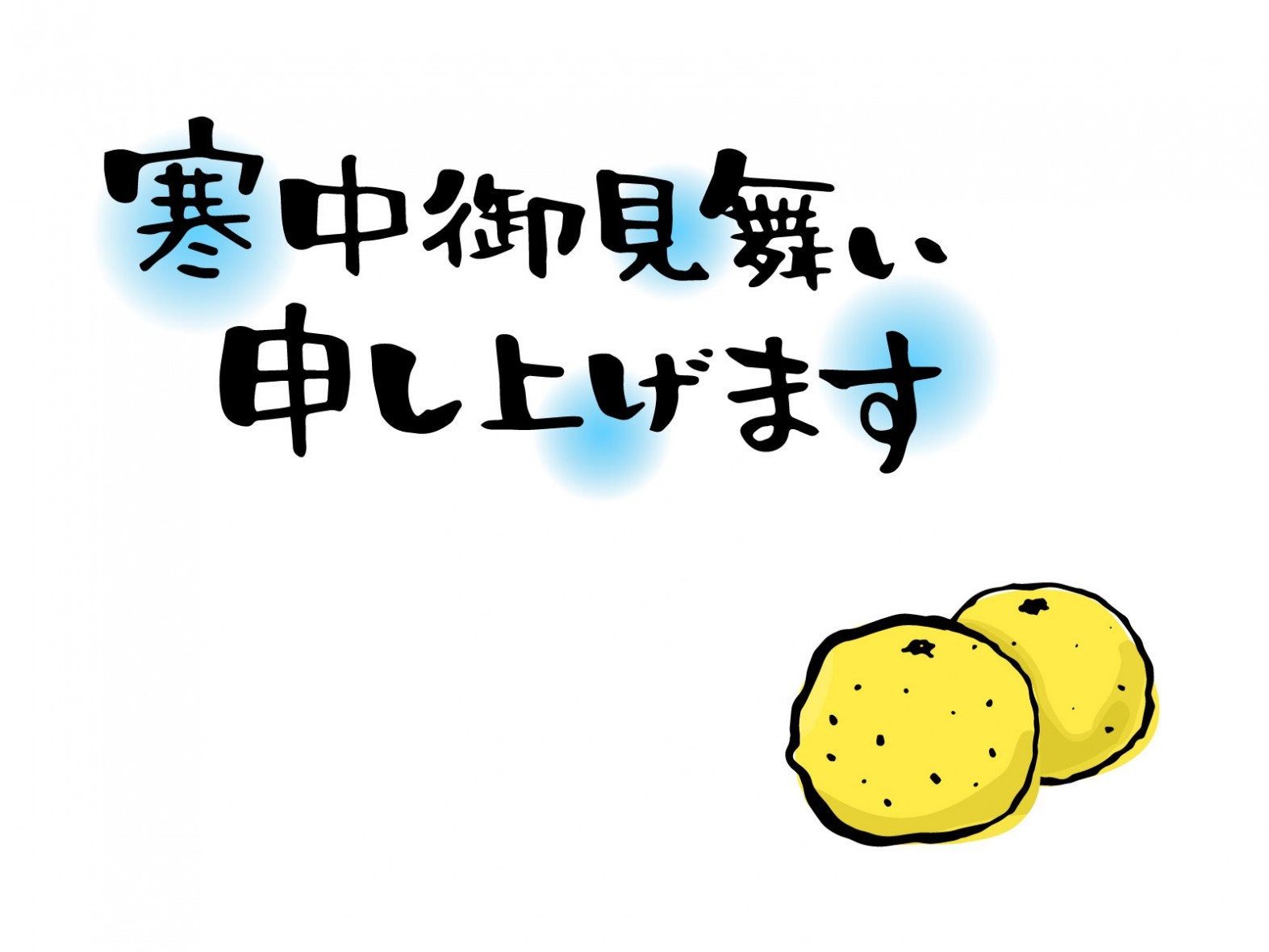引越しは新しい生活のスタートですが、同時に「ご近所付き合い、どうすればいい?」という不安もついてきますよね。
とくに、引越しの挨拶をするかどうか、どこまでの範囲に行くべきか、何を持っていけばいいのかは悩みどころ。
この記事では、戸建て・マンション・一人暮らしなど、状況別に引越し挨拶のマナーをわかりやすく解説します。
最初の印象を良くするためのコツを知って、安心して新生活をスタートさせましょう!
引越しの挨拶は必要?する人が多い理由とは
近年はご近所付き合いが希薄になっているとも言われますが、それでも引越しの挨拶をする人は多くいます。
理由はシンプルで、「顔を知っているだけで安心感が違うから」。
あいさつはお互いを知る第一歩。今後の関係性をスムーズに築くためにも、最初の一声は大切です。
とくに戸建てや子育て世代、社宅・町内会などでは、挨拶が習慣となっているケースも多く見られます。
引越しの挨拶はいつ行くべき?
旧居(今まで住んでいた場所)の挨拶時期
基本的には、引越しの前日〜2日前までが理想です。
ただし、親しくしていたご近所さんには、引越し業者が決まった時点など、もう少し早めに伝えてもいいでしょう。
「突然、明日引っ越します」と伝えるよりも、「近々引越すことになりました」と早めに知らせると印象も良くなります。
このタイミングでは挨拶品は必要ありません。
「長い間お世話になりました」「作業でご迷惑をおかけします」と一言添えるだけで充分です。
新居(引越し先)での挨拶タイミング
新居での挨拶は、引越し当日〜翌日までに済ませましょう。
遅くとも2~3日以内がベストです。訪問は19時くらいまでが理想。夜遅くならないよう配慮が必要です。
訪問時はあまり長居せず、1~2分で済ませるのがマナーです。
不在の場合は、無理に何度も訪ねず、顔を合わせたときに軽く会釈や一言で挨拶するのでも問題ありません。
引越し挨拶に行く範囲は?【戸建て・マンション・社宅】
一戸建ての場合
基本は、「向こう三軒両隣」と「裏側の敷地続きのお宅」。
具体的には以下の通りです:
- 両隣の2軒
- 向かいの3軒(中央+左右)
- 裏側で敷地が接している家(音が響きやすいため)
子どもがいるご家庭では、挨拶範囲を広げておくと安心です。
また、町内会がある地域では、会長さん宅にも先に挨拶しておきましょう。
マンション・アパートの場合
音が伝わりやすい構造のため、基本は**「両隣」と「上下階」**がマナーです。
加えて、管理人さんや自治会の会長さんがいればそちらにも挨拶しておくと良い印象に。
集合住宅では、「顔を合わせた時だけ軽く挨拶する派」も増えてきていますが、最初の印象づくりとして、簡単なあいさつはしておいて損はありません。
社宅の場合
社宅はルールや慣習が決まっているケースが多いため、事前に同僚や管理担当者に確認しておくのがベストです。
特に会社の顔として見られることもあるため、挨拶のマナーには気をつけたいところです。
一人暮らしの引越しも挨拶は必要?
学生や単身の社会人の場合、ご近所との付き合いに距離を置きたい人も多いでしょう。
そのため、最近では「一人暮らしなら挨拶はしない」という選択をする人も増えています。
ただし、挨拶をしておくことで安心感やトラブル防止につながるケースもあります。
判断に迷ったら、まずは管理人さんや大家さんに相談してみるのもおすすめです。
タイミングを逃してしまった場合も、顔を合わせたときに「先日引越してきた○○です」と軽く伝えればOKです。
挨拶品はどう選ぶ?相場とおすすめアイテム
挨拶品の相場は500〜1,000円程度が目安。
高すぎず、気を遣わせない価格帯が好まれます。
おすすめ品は以下のような実用的なもの:
- タオル
- 洗剤(食器用、洗濯用)
- お茶・紅茶
- お菓子(個包装タイプ)
- 乾麺類
⚠️注意したいのは、生ものやかさばるもの。相手の負担になるものは避けましょう。
のし紙は紅白の蝶結びで、「御挨拶」または「粗品」とし、自分の苗字を入れるのが基本です。
名前を入れることで、相手にも覚えてもらいやすくなります。
まとめ|気持ちの良いスタートのために、最初の一歩を大切に
新しい住まいでの生活を気持ちよく始めるためにも、引越しの挨拶はとても大切です。
「どんな人が来たんだろう?」というご近所の不安や好奇心に、ひと声かけるだけでお互いが安心できます。
完璧なマナーよりも、心からの一言とささやかな気配りが、気持ちの良い関係づくりの第一歩になります。
無理をせず、自分らしい挨拶の形を見つけてくださいね。