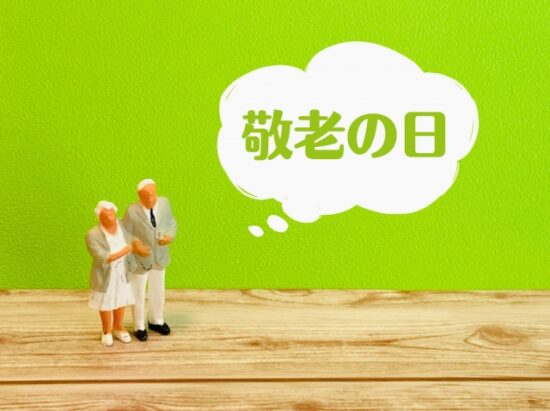「敬老の日」と「老人の日」、名前がよく似ているので混同してしまう方も多いのではないでしょうか。どちらも高齢者を大切にするために設けられた日ですが、実は日付や法律上の位置づけ、目的に違いがあります。
例えば「敬老の日は9月15日」と覚えている方もいれば、「毎年日付が変わるはず」と思っている方もいるかもしれません。その理由は、制度の変更にあるんです。
この記事では、敬老の日と老人の日の違いを歴史や法律の観点から分かりやすく整理しつつ、最近の過ごし方やプレゼントのアイデアまで幅広く紹介します。ご家庭での絆づくりや、学校・地域での取り組みにも役立てていただける内容です。
敬老の日と老人の日の違いを徹底解説!
まずは両者をざっくりと整理しましょう。
-
敬老の日:多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者を敬愛し、長寿をお祝いするための「国民の祝日」。
-
老人の日:高齢者の福祉について理解を広め、自ら生活向上に努める意欲を促すことを目的とした「記念日」。
両者はもともと同じ日(9月15日)でした。しかし2003年にハッピーマンデー制度が導入され、敬老の日が「9月の第3月曜日」に移動。それに伴い、9月15日を「老人の日」として残したのです。
つまり、**「敬老の日=祝日」「老人の日=啓発の日」**というのが大きな違いです。
敬老の日とは?基本情報とお祝いのポイント
敬老の日の由来と法律上の位置づけ
敬老の日の始まりは、兵庫県多可郡野間谷村(現在の多可町)で行われていた「としよりの日」です。1947年に村主導で始まり、1950年代には県全体へ、そして全国へと広がっていきました。
1966年、「国民の祝日に関する法律」によって国民の祝日として制定され、全国的に定着しました。
敬老の日は毎年変わる?日付の仕組み
制定当初は9月15日が固定日でしたが、2003年からは「ハッピーマンデー制度」によって9月の第3月曜日に変更。これにより3連休の一部として親しまれるようになりました。
誰を祝う日?対象となる“敬老”の意味
「敬老の日は何歳から祝うの?」とよく聞かれます。実は、法律上は年齢の基準は決められていません。一般的には70歳前後からと考える家庭が多いですが、孫が生まれたタイミングでお祝いを始めるケースもあります。大切なのは年齢ではなく、感謝の気持ちを伝えることです。
最近の過ごし方
かつては家族で集まって食事をするのが定番でしたが、近年は核家族化や遠方に住むケースも増え、オンラインでのビデオ通話やネット注文でのギフトなど、新しいスタイルのお祝いが広がっています。
老人の日と老人週間の正しい知識
老人の日(9月15日)とは?
敬老の日が移動した後の9月15日は「老人の日」と定められました。これは老人福祉法に基づく日であり、祝日ではありません。
老人週間の期間・意義
9月15日から21日までの1週間は「老人週間」とされています。この期間は全国で高齢者福祉に関するイベントが開かれます。
-
健康診断や介護予防の講演会
-
高齢者施設でのボランティア活動
-
世代間交流イベント
社会全体で高齢者を支える意識を広めるための大切な機会となっています。
老人福祉法とのつながり
老人福祉法の目的は「高齢者の尊厳を守り、福祉の増進を図ること」。老人の日や老人週間は、この法律を具体的に広める取り組みの一つです。
敬老の日と老人の日の違いまとめ
比較表で整理
| 項目 | 敬老の日 | 老人の日 |
|---|---|---|
| 日付 | 9月の第3月曜日 | 9月15日 |
| 根拠法 | 国民の祝日法 | 老人福祉法 |
| 目的 | 高齢者を敬い長寿を祝う | 高齢者福祉への理解を広める |
| 性格 | 国民の祝日(お祝い) | 啓発・理解促進の日 |
呼び名と社会の変化
かつては「老人」という呼び方に抵抗を持つ人も少なくありませんでした。今では「高齢者」「シニア」「ご年配」などの言葉が使われることが多く、呼び名の変化は社会意識の変化を映す鏡でもあります。
家族や地域で気をつけたいこと
「敬老の日のお祝いが逆に年寄り扱いしているようで嫌」という声もあります。無理に形を整えるよりも、「ありがとう」の気持ちをどう伝えるかが一番大切です。
海外の敬老文化と比較
日本だけでなく、世界にも似た風習があります。
-
中国:旧暦9月9日の「重陽節」で年長者を敬う風習
-
韓国:秋夕(チュソク)で祖先や年配者に感謝
-
アメリカ・ヨーロッパ:高齢者の日はなく、感謝祭や地域活動を通じて高齢者を支援
こうした文化を比較すると、日本の「敬老の日」は世界的にも珍しい国民の祝日として高齢者を祝う日であることがわかります。
統計で見る高齢者と社会の変化
総務省の調査(2024年)によると、日本の65歳以上の人口は約3,600万人。総人口の約3割を占め、世界でも有数の高齢社会です。
この背景から、敬老の日は単にお祝いの場にとどまらず、社会全体で高齢者を支える意識を高める日としての役割も大きくなっています。
家族みんなで!敬老の日におすすめのプレゼント・ギフト
贈り物選びのコツ
プレゼントは高価である必要はなく、相手の好みや健康状態に合ったものが喜ばれます。
予算別アイデア
-
1,000円以内:孫からの手作りカード、似顔絵、折り紙作品
-
3,000円以内:花束、和菓子、好きなお茶
-
5,000円以上:旅行券、健康グッズ、温泉や食事の体験ギフト
人気のプレゼント例
花束やお菓子は定番ですが、最近はフォトブックやデジタルフォトフレームなど、思い出を共有できるギフトも人気です。
遠方の祖父母へのお祝い
オンラインショップで注文し、ビデオ通話で一緒にお祝いするスタイルが定着しています。**「顔を見ながらありがとうを伝える」**こと自体が最大のギフトです。
学校・地域での取り組み事例
学校や地域ではさまざまな形で高齢者を敬う活動が行われています。
-
保育園や小学校での「敬老会」:歌や工作のプレゼント
-
地域活動:自治体によるお祝いイベント、健康講座
-
福祉施設:ボランティアの訪問、世代交流イベント
こうした取り組みは、世代を超えた交流を育てる貴重な機会になっています。
よくある質問(Q&A)
Q. 敬老の日と老人の日、両方お祝いするべき?
A. 一般家庭では「敬老の日」に重点を置いていますが、地域や学校では「老人週間」に行事が開かれることがあります。両方を意識するとより理解が深まります。
Q. 「老人」という言葉は失礼じゃない?
A. 法律上は「老人」と表記されていますが、普段の会話では「高齢者」「シニア」と言う方が一般的です。相手に合わせた表現を選ぶのが安心です。
Q. プレゼントは必ず必要?
A. 無理に高価な物を贈る必要はありません。感謝の気持ちを込めた手紙や会話だけでも十分です。
Q. 敬老の日は何歳から祝うの?
A. 法律上の基準はありません。家庭によって異なり、孫ができたタイミングで祝うこともあれば、70歳を目安にすることもあります。
まとめ|敬老の日と老人の日をきっかけに家族の絆を深めよう
敬老の日と老人の日は、どちらも高齢者を大切にするために設けられた大切な日ですが、目的や法律上の性格には違いがあります。
敬老の日は「祝日としてのお祝いの日」、老人の日は「啓発や理解を広める日」。違いを知ることで、より意識を持って過ごせます。
大切なのは、年齢にとらわれることなく「ありがとう」と伝えること。ちょっとしたプレゼントやメッセージでも、気持ちはきっと伝わります。
今年の敬老の日は、家族みんなで温かいひとときを過ごしてみませんか?