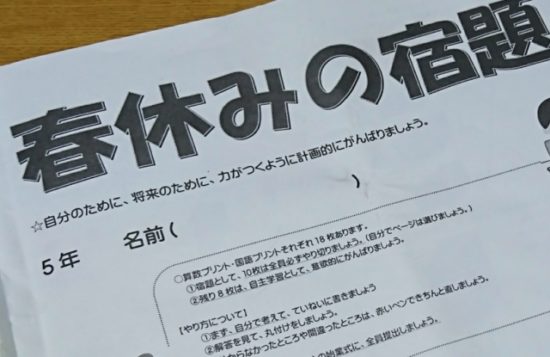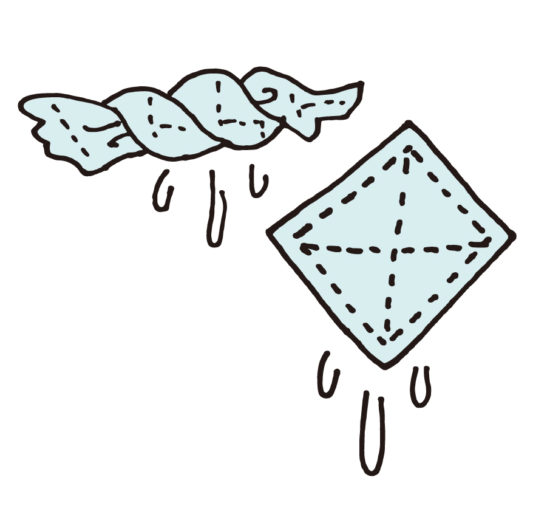「またプリントを出し忘れてる…」
ある日、ランドセルの奥から、くしゃくしゃになったプリントが数枚まとめて出てきました。しかも、その中には提出期限が先週で終わっているものまで…。
そんな瞬間、ため息どころか「なんでもっと早く出さないの!」と声を荒げたくなること、ありますよね。
近年、学校の連絡もメールやアプリで届くようになってきていますが、まだまだ多くの学校では紙のプリントが連絡手段の中心です。
文部科学省の調査でも、オンライン化は地域差が大きく、都市部ではアプリ連絡が普及しつつある一方で、地方では紙がメインのところも少なくありません。
つまり、子どもがプリントを出さない=情報が家庭に届かない。
その結果、大切な行事や手続きに間に合わない…ということも起こり得ます。
プリントを出さないことで起きる困りごと
一見「ただの紙」ですが、学校のプリントには重要な情報が詰まっています。
これを出し忘れると、次のような困りごとが発生します。
-
行事や申込期限を逃す
例えば、運動会の弁当予約や参観日のスケジュールなど、期限が過ぎてしまえばどうにもできません。 -
制服や教材の注文が遅れる
学校指定の業者に直接行かなくてはならず、時間も交通費もかかります。 -
子どもが準備不足になる
遠足や実験授業で必要な持ち物を忘れ、本人が恥ずかしい思いをすることも。 -
先生や他の保護者に迷惑がかかる
提出物の遅れは、先生のスケジュール調整や印刷枚数の変更を発生させます。
こうしたトラブルは、小さくても積み重なると親も子も疲弊してしまいます。
学年別・子どもがプリントを出さない主な理由
低学年(1〜2年生)
-
おやつや遊びに気持ちが向いてしまい、プリントの存在を忘れる
-
「持ち帰る」ことがまだ生活習慣に組み込まれていない
例:帰宅後すぐランドセルを放り投げ、テレビをつける→プリントは翌日まで発見されない
中学年(3〜4年生)
-
整理整頓が苦手で机やランドセルが物でいっぱい
-
連絡袋やファイルに入れるのを面倒に感じる
例:ランドセルの底から数週間前のプリントが3枚重なって出てくる
高学年〜中学生
-
思春期で親との会話を避ける傾向が強い
-
命令されると反発したくなる心理
-
自分のペースを乱されたくない
例:「後でやる!」と言ったまま夜まで忘れる→親と口論になる
タイプ別!プリントを出させる工夫
忘れっぽいタイプ
-
即時声かけ:「プリントは?」を帰宅直後に
-
「後で」はNG。「今やろうね」と促す
-
毎日同じタイミングで確認することで習慣化
実践ポイント:冷蔵庫や玄関に「プリント出す!」のメモを貼ると親も忘れにくい
面倒くさがりタイプ
-
ファスナー付き連絡袋より、入れるだけのクリアファイル
-
机でプリントをもらった瞬間にファイルに入れるルール
-
余計な動作を省いてハードルを下げる
注意点:ファイルの中身は週1回チェックしないと“紙の墓場”になる
思春期タイプ
-
淡々と短く声かけ(説教は逆効果)
-
「今日は何かお知らせあった?」と自然に聞く
-
感情的にならず“事務連絡”のように扱う
実践ポイント:LINEやメモでやりとりする方法も効果的
すぐ使える!声かけ例文集
-
優しい口調:「今日は何かお知らせあった?」
-
ユーモア混じり:「プリント警察でーす!捜査開始!」
-
習慣化ルール:「ただいま → 手洗い → プリント」
声かけを日替わりにすることで、子どもも飽きずに反応してくれます。
親が疲弊しないための工夫
-
確認は1日1回だけにして、必要以上にエネルギーを使わない
-
兄弟姉妹と協力して声かけを分担
-
週末にまとめて整理して、プリントの山を防ぐ
ワンポイント:全プリントを一時置きする「家族用プリントBOX」を作ると、散らかり防止にも◎
便利グッズ・アプリで管理をラクに
物理アイテム
-
A4クリアファイル(色分け推奨):兄弟別や用途別に色分け
-
マグネット式掲示ボード:冷蔵庫横など目に入る場所に設置
-
壁掛けポケット:行事用、提出用、保存用に分けられる
デジタルツール
-
プリント管理アプリ:写真で撮ってデータ化
-
Googleカレンダー連携:行事や提出期限を自動で通知
実践例:プリントをスマホで撮影→家族共有フォルダに保存→期限が近づいたらアラート通知
習慣化には「3週間ルール」を参考に
-
一般的に「新しい習慣は3週間で定着しやすい」と言われるが、実際には平均66日かかるという研究もあり個人差が大きい
-
最初は親主導でOK、徐々に子どもに任せる
-
成功した日はしっかり褒めることで継続力がアップ
心理的背景:人は「達成感」が続くことで行動を繰り返す傾向があるため、小さな成功でも評価してあげることが大切
まとめ(行動を促す)
プリントを出す習慣は、将来社会で必要になる「書類提出力」の第一歩です。
これは単なる親のイライラ解消ではなく、子どもの自立につながる大切なトレーニング。
子どものタイプに合わせた方法と声かけで、無理なく習慣づけていきましょう。
そして、自分からプリントを出せるようになった日には、「成長したな」と思うと同時に、少し寂しさも感じるかもしれません。
でも、それは子どもが一歩ずつ社会に向かって成長している証拠です。温かく見守りながら、その日を迎えましょう。
合わせて読みたい ⇒ 授業参観を嫌がる子の理由と親の対応法|「来ないで」と言われたときの具体策