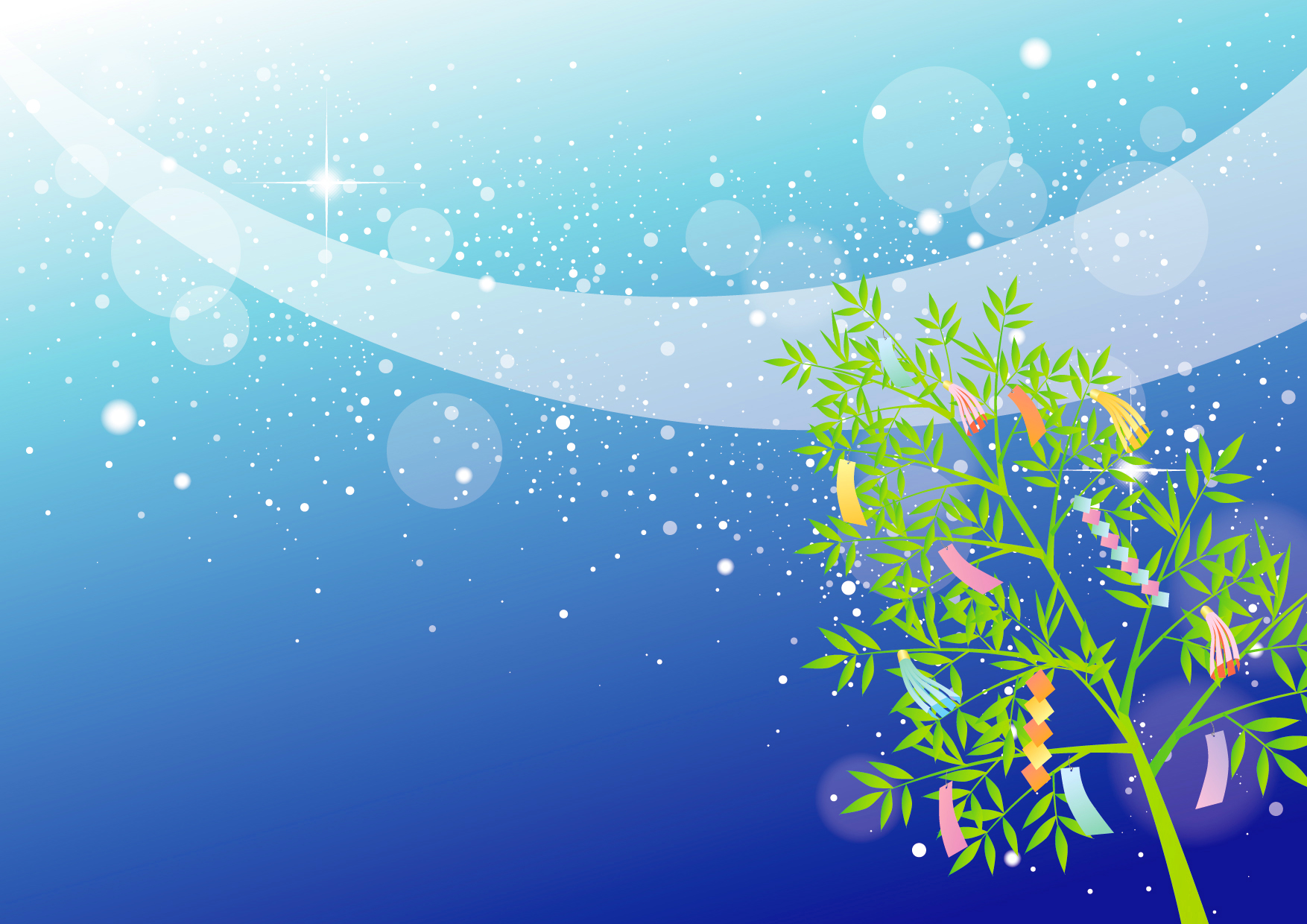7月7日の夜に行われる「七夕(たなばた)」。
大人にとっては当たり前の行事でも、子供にとっては「なんで短冊に願い事を書くの?」「どうして天の川が関係あるの?」と、不思議がいっぱいです。
この記事では、子供にもわかる七夕の由来や簡単なあらすじ、名前の読み方の秘密、星座や短冊の意味、地域ごとの違い、さらには親子で楽しむ工夫までたっぷりご紹介します。
「七夕ってなに?」と聞かれたとき、そのまま読んで聞かせられる“ミニ絵本+豆知識集”として活用できます。

七夕の由来|子供にやさしい簡単あらすじ
むかしむかし、天の川のほとりに、機織りがとても上手な天の神様の娘・織姫(おりひめ)と、牛の世話をまじめにこなす青年・彦星(ひこぼし)がいました。
神様が二人を引き合わせると、一目で恋に落ちて結婚。ところが仲が良すぎるあまり、毎日遊んでばかりで、織姫は機織りをやめ、彦星も牛の世話をしなくなってしまいました。
これに怒った神様は、二人を天の川の両岸に引き離します。悲しみに暮れる織姫を見た神様は、こう条件を出しました。
「まじめに働くなら、1年に1度だけ会わせてあげよう」
こうして二人は、毎年7月7日の夜にだけ天の川を渡り、再会できるようになりました。
このお話は、中国の「七夕節」に由来し、日本では奈良時代に伝わってきたとされています。
親子で話すときの一言例
「織姫と彦星はね、会えるのは年にたった1回だけ。でもその日を楽しみに毎日頑張って働くんだよ」
「七夕(たなばた)」という名前の由来
「七夕」と書いて「たなばた」と読むのは不思議ですよね。
この読み方は、日本古来の神事「棚機(たなばた)」に由来します。
古代日本では、村を水害や災いから守るため、清らかな乙女が水辺の機屋(はたや)にこもり、神様に捧げる織物を織る風習がありました。
この乙女を「棚機津女(たなばたつめ)」と呼び、その名前が現在の「たなばた」という読み方につながったのです。
奈良時代に中国の七夕伝説が伝わると、機織りの女性という共通点から、この日本の風習と融合。江戸時代には庶民にも広まり、盆行事や習い事の上達祈願と結びついて、現在の七夕の形が定着しました。
七夕の星座と天の川の関係
七夕の夜空を彩るのが、こと座のベガ(織姫星)と、わし座のアルタイル(彦星)。
二つの星の間に天の川が流れ、その橋を渡って二人が会うと伝えられています。
星の探し方
-
7月上旬の夜9時頃、東の空を見上げる
-
明るく白く輝く星の中で、最も目立つのがベガ(織姫星)
-
そこから少し離れた場所にある明るい星がアルタイル(彦星)
さらに、二人の星の近くには白鳥座のデネブがあり、この三つを結ぶと「夏の大三角形」と呼ばれます。
親子で夜空を見ながら探してみると、まるで物語の中に入り込んだような気分になれます。

七夕の日が雨だとどうなる?
「七夕の日に雨が降ると、二人は会えない」と言われますが、中国の伝説ではもうひとつ別の説もあります。
それは「カササギ(鵲)が翼を広げて橋をつくり、二人を会わせてくれる」というもの。
雨の日でも二人は雲の上で会っているかもしれない、そう想像するとロマンチックですよね。
雨の七夕は、室内で七夕飾りを作ったり、星や天の川の絵を描いて過ごすのもおすすめです。
地域ごとの七夕行事と日付の違い
日本の多くの地域では7月7日に七夕を行いますが、旧暦に合わせて8月上旬に行う地域もあります。これは、梅雨明け後のほうが天の川がよく見えるためです。
有名な七夕まつり
-
仙台七夕まつり(宮城県)…豪華な吹き流しが街を彩る。毎年8月6〜8日開催
-
湘南ひらつか七夕まつり(神奈川県)…色とりどりの飾りと屋台がにぎやか
-
一宮七夕まつり(愛知県)…市内一帯で飾りやイベントを楽しめる
同じ七夕でも、地域によって飾りや催し物が異なります。旅行先で体験するのも素敵です。
短冊の意味と色ごとの願い
七夕の短冊は、もともと織姫のように技術が上達することを願って飾られました。
笹は生命力が強く、悪いものを追い払うとされ、願い事を守ってくれる象徴でもあります。
五色の短冊の意味(五行説)
-
青(緑)…徳を積む、人として成長
-
赤…感謝や家族への思い
-
黄…人間関係や信頼
-
白…義務や約束を守る
-
黒/紫…学業や知識の向上
家族で色を分けて飾ると、それぞれの願いがより特別に感じられます。
七夕飾りの種類と意味
短冊だけでなく、七夕飾りには次のような種類があります。
-
吹き流し…織姫の糸を表し、技芸上達を願う
-
網飾り…豊漁・豊作祈願
-
折り鶴…長寿祈願
-
巾着…商売繁盛や金運上昇
折り紙や紙テープで作れるものが多く、親子で工作すれば楽しい思い出に。
七夕に食べるものと由来
七夕にそうめんを食べる習慣は、平安時代ごろに中国から伝わった「索餅(さくべい)」という小麦料理が起源という説や、細長い麺を織姫の糸や天の川に見立てたという説があります。
由来は諸説ありますが、夏らしい涼やかな料理として定着しました。
地域によっては七夕団子や、星型に抜いた野菜を使った料理も。
「天の川ゼリー」や「星形クッキー」など、子供と一緒に作れるメニューも人気です。
親子で楽しむ七夕の過ごし方

-
おうちで七夕飾りづくり…折り紙や画用紙で短冊・飾りを作る
-
星空観察…アプリで星座の位置を確認しながら探す
-
願い事の書き方…「〜できますように」より「〜する!」と前向きに書くと叶いやすいとされます
-
記念写真…笹や星空を背景に撮影し、SNSやアルバムに残す
まとめ
-
七夕は、中国の伝説と日本の古い神事「棚機」が融合してできた行事。
-
短冊や笹には、上達祈願や魔除けの意味がある。
-
七夕飾りやそうめんなど、楽しみ方は地域や家庭ごとにさまざま。
今年の七夕は、夜空を見上げながら家族で願い事を語り合ってみませんか?
晴れた夜には天の川が見えるかもしれませんし、雨の日でも心温まる七夕を楽しめます。